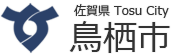本文
企画展「昔、戦争があった-鳥栖空襲と人々の暮らし-」
開催期間
終戦80年企画展
令和7年8月1日(金曜)~24日(日曜)

<展示全景>
はじめに
今年で太平洋戦争終戦から80年を迎えます。
鳥栖市教育委員会では、鳥栖空襲で被災した8月11日にあわせて戦争に関する展示を行っています。今回は「昔、戦争があった -鳥栖空襲と人々の暮らし-」というテーマで展示を企画しました。
本展示では、戦時中の鳥栖を映した写真や戦地から送られた手紙、実際に戦時中に使用された道具などを展示しています。当時の人々がどのような思いで生活していたのか、その生活はどのような様子だったのかを知ることができます。また、現在の鳥栖市に残る戦争の痕跡についても取り上げています。
太平洋戦争後、日本ではこのようなことを二度と起こさないために終戦から現在に至るまで平和主義を憲法に掲げ、争いを行わない国として存在しています。