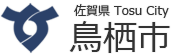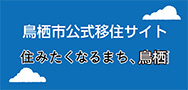本文
障害者差別解消法について
障害者差別解消法とは
平成28年4月1日に、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が施行されました。この法律は、障害のある人への差別をなくすことで、障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合い、支えあいながら、共に生きる社会、誰もが安心して暮らせる社会をつくることを目指しています。
令和3年5月にこの法律は改正され、令和6年4月1日から事業者による合理的配慮の提供について義務化されました。
国民・行政機関等・事業者の責務
この法律では、国民の責務として、障害を理由とする差別の解消の推進できるよう努めるとともに、国及び地方公共団体の責務として、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、実施することを定めています。
さらに、行政機関等及び事業者は、障害を理由として不当な差別的取扱いをすることにより障害者の権利利益を侵害してはならないと定めるとともに、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の状況に応じて、必要かつ合理的な配慮を行うこととされています。これまでは行政機関等には義務として、事業者には努力義務として定められていましたが、令和3年5月にこの法律は改正され、令和6年4月1日からは事業者にも義務として定められました。
参考 【障害者差別解消法・条例】合理的配慮の提供ハンドブックや佐賀県みんなで支えるけん!について / 佐賀県 (saga.lg.jp)<外部リンク>
不当な差別的取り扱いの禁止と合理的配慮
不当な差別的取り扱いとは、障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
例えば
・受付の対応を拒否する。
・本人を無視して介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかける。
・学校の受験や、入学を拒否する。
・障害者向け物件はないと言って対応しない。
・保護者や介助者が一緒にいないとお店に入れない。
参考:内閣府 リーフレット「「合理的配慮」を知っていますか?」
このような差別を禁止することとなっています。
また、障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な合理的な配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障害のある人の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。
例えば
・障害のある人の障害特性に応じて、座席を決める。
・障害のある人から、「自分で書き込むのが難しいので代わりに書いてほしい」と伝えられたとき、代わりに書くことに問題がない書類の場合は、その人の意思を十分に確認しながら代わりに書く。
・意思を伝えあうために絵や写真のカードやタブレット端末などを使う。
・段差がある場合に、スロープなどを使って補助する。
参考:内閣府 リーフレット「「合理的配慮」を知っていますか?」
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)