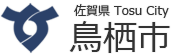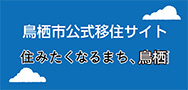本文
ひとり親家庭医療費助成
助成内容
母子家庭、父子家庭の方等が、健康保険により医療機関等で診療を受けた場合、医療費の自己負担金を助成します。(但し1ヶ月につき一人500円の自己負担あり)
助成対象者
母子(父子)家庭の母(父)とその養育する児童、父母のない児童で、所得が一定の基準(児童扶養手当の所得限度額と同じ)を超えない世帯。
母子(父子)家庭の母(父)…20歳未満の児童を養育している者
児童…18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者
助成制限
助成の要件に該当しても、次のいずれかに該当する場合は、助成されません。
父、母が婚姻の届をしていなくても、事実上婚姻関係と同様の実情にあるとき
請求者、同居の家族の方の前年所得が一定額(下の表)以上あるとき
所得制限
助成対象者や、同居の親族等の前年の所得が下記の限度額以上ある場合は、その年度(9月~翌年の8月まで)は、助成が受けられません。
|
所得制限限度額表 |
||
|---|---|---|
|
扶養親族の数 |
本人限度額 |
配偶者及び扶養義務者・孤児等の養者 |
|
0人 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
|
1人 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
|
2人 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
|
3人以上 |
以下380,000円ずつ加算 |
以下380,000円ずつ加算 |
請求者本人に、老人扶養親族がある場合は100,000円、特定扶養親族がある場合は150,000円が限度額に加算されます。
助成を受けるには?
1.支払
いったん医療機関に全医療費の3割相当分の一部負担金を支払う。
2.申請
受診をした月の翌月以降に、受診者ごと、医療機関(総合病院は診療科)ごと、月ごとに領収書をまとめて「ひとり親家庭等医療費助成申請書」を提出。申請書は、こども育成課にあります。(申請書は、コピー可)
★こちらからダウンロードもできます⇒助成申請書 [Wordファイル/44KB] 助成申請書 [PDFファイル/103KB]
★電子申請も利用できます⇒ひとり親家庭等医療費助成金申請<外部リンク>
3.振込
原則として、申請した翌月末に、保険適用分から1ヶ月1人につき500円を控除した額を、指定口座に払戻します。
ご注意ください!!
助成対象外となるもの
- 保険が適用されないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、文書料、入院時の食事代、差額ベッド代等)
- 受診月の翌月から1年を過ぎた場合(例:R1.5月診療→R1月6日.1~R2.5.31まで申請可能)
高額療養費
ご加入の健康保険組合が、高額療養費の支給額を決定してからの申請となります。高額療養費支給額決定通知書(もしくは『健康保険限度額適用認定証』)、領収書(コピー可)を添えて「ひとり親家庭等医療費助成申請書」で払戻の申請をしてください。
『健康保険限度額適用認定証』をご利用ください!
医療機関に支払う前に、ご加入の健康保険組合で『健康保険限度額適用認定証』の手続きをすると、自己負担限度額までの支払ですみます。詳しくは、ご加入の健康保険組合へお問合せください。
補装具代
コルセット等補装具代を支払ったときは、医師の証明書、領収書(コピー可)、健康保険の支給決定通知書の写しを添えて、「ひとり親家庭等医療費助成申請書」で払戻の申請をしてください。
子どもの医療費助成の資格をお持ちのお子さんについて
- 6歳の年度末までは、子どもの医療での助成が優先です。
- 小学生以上のお子さんが受診された場合は、ひとり親家庭等医療費助成か子どもの医療費助成かを選択することができます。
ひとり親家庭等医療費助成を選択される場合は、病院等の窓口で子どもの医療の資格証は提示せず、いったん全額お支払いください。その後、こども育成課窓口でひとり親家庭等医療費助成の申請をしてください。
子どもの医療の資格証を利用された場合は、ひとり親家庭等医療費助成の申請はできませんのでご注意ください。
学校でのケガ
学校等でケガをした場合は、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が優先となります。ひとり親家庭等医療費助成や、子どもの医療費助成と重複して助成を受けることはできません。
更新手続
ひとり親家庭等医療費助成は、前年の所得状況と現在の養育状況などを確認するため、毎年8月に更新手続が必要になります。更新手続を行なわないと、継続して医療費の助成を受けることができなくなります。対象者には8月上旬にお知らせを郵送いたしますので、必ず手続きを行ってください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)