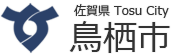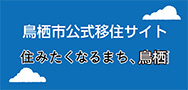本文
「子どもの権利」について
「子どもの権利」について
「子どもの権利条約」とは
子どもの権利条約は、子どもは「弱くておとなから守られる存在」という考え方から、それだけではなくて、子どもも「ひとりの人間として人権(権利)をもっている」、つまり、「権利の主体」だという考え方に大きく転換させた条約です。子どもを権利の主体ととらえ、おとなと同様にひとりの人間としてもつ様々な権利を認めると同時に、成長の過程にあって保護や配慮が必要な子どもならではの権利も定めているというのが、子どもの権利条約の特徴です。
子どもの人権を守りましょう(法務省)<外部リンク>
「子どもの権利条約」の4つの原則
1.差別の禁止(差別のないこと)
すべての子どもは、子ども自身や親の人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも左右されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。
2.子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)
子どもに関することが決められ、行われる時は、「その子どもにとって最もよいことは何か」を第一に考えます。
3.生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)
すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。
4.子どもの意見の尊重(子どもが意味のある参加ができること)
子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。
こども向け解説
「子どもの権利条約」ってなに?
全世界のすべてのこどもたちが幸せに毎日くらすことができたらいいと思いませんか。でも、世界には貧しさに苦しんで食べものがない家族もいます。災害や戦争、紛争でふるさとをなくして家族と別れ、学校にも通えないこどもたちがたくさんいます。日本でも、おとなにひどい目にあわされたり、嫌なことをされたりするこどもたちがいます。
そのような厳しい状況にある多くのこどもたちがいることから、世界の国々の責任として、こどもの権利をしっかりと守っていくために、1989年につくられたのが「こどもの権利条約です」です。どんな内容にしたらよいか、多くの国や国際機関等が長い間話し合って決めました。
「子どもの権利条約」4つの原則
1.差別されない
人種や性別、使う言葉、信じている宗教、親がどのような人か、障がいの有無・・・どのような違いがあっても差別されません。
もし、あなたが差別されて苦しんでいるなら助けを求めてください。
2.あなたが一番
大人は、「あなたにとって最もよいことは何か」をいつも考えなければなりません。
あなたの人生は、大人の都合だけで決められてよいものではありません。
3.守られる命
すべてのこどもには生きる権利があります。
あなたは、すこやかな成長のために、十分な教育や支援を受けることができます。
4.意見は大切
あなたの意見は、あなたの年齢や成長に応じて、しっかりと尊重されます。
意見があれば、伝えてみましょう。
「こども基本法」とは
概要
こども基本法は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、すべてのこどもが、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指し、こども政策を総合的に推進することを目的としています。同法は、こども施策の基本理念のほか、こども大綱の策定やこども等の意見の反映などについて定めています。
こども基本法(こども家庭庁)<外部リンク>
「こども施策6つの基本理念」
1.すべてのこどもは大切にされ、基本的な人権が守られ、差別されないこと。
2.すべてのこどもは大事に育てられ、生活が守られ、愛され、保護される権利が守られ、平等に教育が受けられること。
3.年齢や発達の程度により、自分に直接関係することに意見を言えたり、社会のさまざまな活動に参加できること。
4.すべてのこどもは年齢や発達の程度に応じて、意見が尊重され、こどもの今とこれからにとって最もよいことが優先して考えられること。
5.子育ては家庭を基本としながら、そのサポートが十分に行われ、家庭で育つことが難しいこどもも、家庭と同様の環境が確保されること。
6.家庭や子育てに夢を持ち、喜びを感じられる社会をつくること。