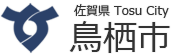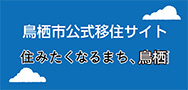本文
高齢者の予防接種
鳥栖市では、予防接種法によって定められている定期の予防接種を指定医療機関で個別接種により実施しています。
対象年齢・接種期間に該当する人は、費用の一部負担で接種が受けられます。
予防接種の種類
高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種
肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。日本人の約3~5%の高齢者では、鼻やのどの奥に菌が常在しているとされています。
肺炎球菌感染症の予防接種では、1回の接種で肺炎球菌の23種類の型に対して免疫をつけることができます。
※すでに23価肺炎球菌ワクチンを接種したことがある人は対象となりません。
※令和8年4月からより効果の高いワクチンに変更されます。それに伴い接種費用も変更する可能性があります。
対象者、接種期間、接種費用
| 対象者 | 接種期間 |
接種費用 (自己負担額) |
|---|---|---|
| 65歳の方 |
65歳の誕生日の前日から 66歳の誕生日の前日まで |
2,500円 生活保護者は無料 ※非課税世帯は無料の対象ではありません。 |
|
60歳から65歳未満の方で、 心臓や腎臓、呼吸器の機能の障害により身のまわりの生活を極度に制限される人、または、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫機能の障害により日常生活がほとんど不可能な人 (身体障害者手帳1級相当) |
60歳から65歳未満の間 |
接種方法
実施医療機関に直接予約をお願いします。予防接種実施医療機関一覧(肺炎球菌、帯状疱疹) [PDFファイル/128KB]
※実施医療機関以外で接種をご希望の方は、鳥栖市保健センター(0942-85-3650)にご連絡ください。
帯状疱疹の予防接種
ヘルペスウイルスにより引き起こされる帯状疱疹や合併症の重症化を予防するため、定期接種(B類)として実施されます。
ヘルペスウイルスは、はじめて感染(いわゆる「水ぼうそう」)した後、生涯にわたって神経に潜伏感染し、加齢・疲労・免疫低下によってウイルスが再活性化することで帯状疱疹が起こります。主な症状は、ウイルスが感染した神経が支配する領域の皮膚に帯状に出現する、時に痛みを伴う水疱です。合併症の一つに、皮膚症状が治った後も数か月から数年にわたり痛みが残る「帯状疱疹後神経痛」があります。帯状疱疹の発症年齢は70歳代が最も多くなっています。
対象者
下記(1)(2)のいずれかに当てはまり、接種日時点で鳥栖市に住民票がある方。
(1)65歳以上で下表に該当する方。66歳以上は令和7~11年度の5年間の経過措置期間のみ対象。101歳以上は令和7年度のみ対象。
【帯状疱疹 定期予防接種 対象年度早見表 [PDFファイル/438KB]】 [PDFファイル/438KB]
(2)接種日時点で 60~64歳で、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方(身体障害者手帳1級相当)
※上記(1)(2)に該当する場合でも過去に帯状疱疹予防接種を受けたことがある方は原則定期予防接種の対象外ですが、医師が必要と認めた場合は対象となることがあります。
※2回接種が必要なワクチンで1回分のみ接種済みの場合は、残りの1回分を定期接種として取り扱うことができます。
|
生ワクチン |
組換え(不活化)ワクチン |
||
|---|---|---|---|
| 接種条件 |
病気や治療により免疫の低下している方は接種できません。 |
免疫の状態に関わらず接種可能。 |
|
| 接種回数・方法 |
1回のみ 皮下注射 |
2か月の間隔をあけて2回※ 筋肉内注射 |
|
|
費用(自己負担額) ※生活保護者は無料 |
2,500円 |
6,500円/回 | |
| 発症予防効果 | 接種後1年 | 6割程度 | 9割以上 |
| 接種後5年 | 4割程度 | 9割程度 | |
| 接種後10年 | ― | 7割程度 | |
| 副反応 | 70%以上 | ― | 接種部位の疼痛 |
| 30%以上 | 注射部位の発赤 | 注射部位の発赤、筋肉痛、疲労 | |
| 10%以上 | 注射部位の掻痒感、熱感、腫脹、疼痛、硬結 | 注射部位の腫れ、胃腸症状、悪寒、発熱 | |
| 1%以上 | 発疹、倦怠感 | 痒み、倦怠感、全身疼痛 | |
| 特に注意を要する副反応 | 頻度は不明ですが、アナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、無菌性髄膜炎がみられることがあります。 | 頻度は不明ですが、ショック、アナフィラキシーがみられることがあります。 | |
※ワクチンの種類は1種類しか選択できません。
※組換え(不活化)ワクチンは、期間内に2回の接種を終了できるよう初回を令和8年1月までに接種してください。
※病気や治療により免疫機能が低下している(する可能性がある)方は、医師が早期接種を必要と判断した場合、接種期間を1か月に短縮することができます。
※接種間隔が2か月を超えた場合は6か月後までに2回目を接種をしますが、2回目が定期接種対象期間を超えた場合は定期外です。定期接種対象期間内であれば6か月を超えた場合でも定期として接種できます。
※接種後、気になる症状を認めた場合は、接種した医療機関へお問い合わせください。
接種期間、接種方法
令和7年度の接種期間は令和7年4月1日~令和8年3月31日です。
※組換え(不活化)ワクチンは、期間内に2回の接種を終了できるよう初回を令和8年1月までに接種してください。
2種類のワクチンがあり、医療機関によって取り扱うワクチンの種類が異なります。医療機関へ直接ご確認ください。
帯状疱疹予防接種実施医療機関に直接予約をお願いします。予防接種実施医療機関一覧(肺炎球菌、帯状疱疹) [PDFファイル/128KB]
※実施医療機関以外で接種をご希望の方は鳥栖市保健センター(0942-85-3650)にご連絡ください。
インフルエンザの予防接種
インフルエンザは、インフルエンザウイルスに感染することによって起こります。
インフルエンザの流行は、通常、初冬から春先にみられますが、ときには春期、夏期にもみられます。
インフルエンザ予防接種を受けてからインフルエンザに対する抵抗力がつくまでに2週間程度かかり、その効果が十分に持続する期間は約5か月間とされています。より効率的に有効性を高めるためには、毎年インフルエンザが流行する前の12月中旬までの間に接種を受けておくことが望ましいとされています。
対象者、接種期間、接種費用
| 対象者 | 接種期間 |
接種費用 (自己負担額) |
|---|---|---|
| 65歳以上の方 |
令和7年10月1日から 令和8年1月31日まで |
1,000円
生活保護者は無料。 ※非課税世帯は無料の対象ではありません。 |
|
60歳から65歳未満の方で、 心臓や腎臓、呼吸器の機能の障害により身のまわりの生活を極度に制限される人、または、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害により日常生活がほとんど不可能な人 (身体障害者手帳1級相当) |
接種方法
実施医療機関に直接予約をお願いします。
高齢者インフルエンザ予防接種実施医療機関を確認する↠高齢者インフルエンザ予防接種実施医療機関一覧 [PDFファイル/114KB]
※実施医療機関以外で接種をご希望の方は、鳥栖市保健センター(0942-85-3650)にご連絡ください。
新型コロナウイルス感染症の予防接種
新型コロナは、新型コロナウイルスに感染することによって起こります。
令和6年度以降の新型コロナワクチンの接種については、個人の重症化予防により重症者を減らすことを目的とし、定期接種(B類)として実施することとなっています。
対象者、接種期間、接種費用
| 対象者 | 接種期間 |
接種費用 (自己負担額) |
|---|---|---|
| 65歳以上の方 |
令和7年10月1日から 令和8年3月31日まで |
3,000円 生活保護者は無料。 ※非課税世帯は無料の対象ではありません。 |
|
60歳から65歳未満の方で、 心臓や腎臓、呼吸器の機能の障害により身のまわりの生活を極度に制限される人、または、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害により日常生活がほとんど不可能な人 (身体障害者手帳1級相当) |
接種できるワクチン
| mRNAワクチン | 組替えタンパクワクチン |
|---|---|
| ファイザー社 | 武田薬品工業社 |
| モデルナ社 | |
| 第一三共社 | |
|
Meiji Seika ファルマ社(レプリコンワクチン) |
新型コロナワクチンQ&A(出典:厚生労働省ホームページより一部抜粋)
(1) mRNA(メッセンジャーRNA)ワクチンは新しい仕組みのワクチンということですが、どこが既存のワクチンと違うのですか。
mRNAワクチンは、ウイルスのたんぱく質を作る基になる遺伝情報の一部を注射します。
体内で産生されるウイルスのタンパク質に対する抗体などが体内で作られることにより、ウイルスに対する免疫ができます。
(2)「レプリコンワクチン」は、どのようなワクチンですか。既存のmRNAワクチンとどこが違うのですか。
レプリコンワクチンはmRNAワクチンに比べてウイルスのタンパク質が作られる期間が長いという特徴があります。
このため、既存のmRNAワクチンよりも強く免疫が誘導され、抗体の持続期間が長いことが確認されています。
(3)「組換えタンパクワクチン」とはどのようなワクチンですか。
組替えタンパクワクチンは、新型コロナウイルスの表面にあるスパイクタンパク質の遺伝子をもとに作られた組替えタンパク質を有効成分とするワクチンです。接種後、ヒトの体内でスパイクタンパク質に対する免疫が誘導されることで、新型コロナウイルス感染症の予防ができると考えられています。
接種方法
実施医療機関に直接予約をお願いします。
高齢者新型コロナウイルス予防接種実施医療機関を確認する↠高齢者新型コロナウイルス予防接種実施医療機関一覧 [PDFファイル/109KB]
※実施医療機関以外で接種をご希望の方は、鳥栖市保健センター(0942-85-3650)にご連絡ください。
関連情報
新型コロナワクチン定期接種について [PDFファイル/1012KB](厚生労働省作成リーフレット)
厚生労働省ホームページ:新型コロナワクチンについて<外部リンク>
厚生労働省ホームページ:新型コロナワクチンQ&A<外部リンク>
任意接種について
定期接種の対象者以外の方及び接種期間外の接種は、すべて任意接種になります。
具体的な金額や使用するワクチンの種類、実施期間等は、医療機関によって異なります。直接、医療機関へお問合せください。
予防接種済証や記録について
●予防接種済証の再交付について●
高齢者の予防接種は、接種後「予防接種済証」を発行していますが、紛失などで再発行を希望の方については、「予防接種済証再交付申請書 [PDFファイル/51KB]」を鳥栖市保健センターへ提出いただくと、再交付することができます。ご希望の方は、鳥栖市保健センター(0942-85-3650)にご連絡ください。
●予防接種済の記録について●
予防接種の記録について、ご自身で管理していただけるように国立感染症研究所が作成した「成人用予防接種記録手帳」をご紹介します。
ご利用を希望される際は、リンク先から「成人用予防接種記録手帳」を開いていただき、ご自身でプリントアウトしてご活用ください。
具体的な金額や使用するワクチンの種類、実施期間等は、医療機関によって異なります。直接、医療機関へお問合せください。
出典:国立感染症研究所ホームページ(https://www.niid.go.jp/niid/ja/vaccine-j.html)<外部リンク>
予防接種健康被害救済制度について(鳥栖市ホームページ:関連記事ID0049021)
ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったり死亡された場合において、そのような状況がワクチン接種を受けたことによるものと厚生労働大臣が認定した時には、予防接種法に基づき救済(医療費・障害年金等の給付)が受けることができます。
なお、現在の救済制度の内容については、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご参照ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)