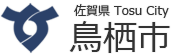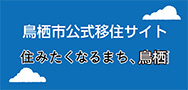本文
障害福祉サービスについて
障害福祉サービスには、それぞれの方の障がいの程度や社会活動、介護者、住居等の状況を踏まえ、個別に支給決定が行なわれる「障害福祉サービス」と、市の創意工夫により、地域・利用者の状況に応じて柔軟に対応できる「地域生活支援事業」に大別され、「障害福祉サービス」には、介護の支援を受ける場合の「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合の「訓練等給付」の2つがあります。
なお、65歳以上(介護保険制度で定められた特定疾病による場合は40歳以上)の方は、介護保険制度が優先されます。
訪問・通所系サービス
利用者が在宅でホームヘルパーの訪問などのサービス利用、施設に通って利用するデイサービスなどがあります。
日中活動と居住支援
入所施設で提供されるサービスもあります。サービス利用者が入所施設内だけの生活にとどまらず地域社会とのかかわりのある暮らしを実現するために、入所施設で昼間の活動を支援する「日中活動」と住まいの場における「居住支援」に分かれています。
申請からサービス利用までの流れ
障害福祉サービスを利用するためには、市町村にサービス利用申請をして審査、判定を受ける必要があります。その結果、障害程度区分が決定され受給者証が交付されます。利用者は、サービス提供事業者と契約し、サービスの利用が始まります。
障害者総合支援法の対象となる障害者は、以下の要件が必要です。
- 身体障害者福祉法に規定されている身体障害者
- 知的障害者福祉法に規定されている知的障害者のうち18歳以上の者
- 精神保健および精神障害者福祉に関する法律に規定されている精神障害者のうち18歳以上の者
- 児童福祉法に規定されている障害児および精神障害者のうち18歳未満の者
- 難病等(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるもの)による障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者
サービス利用の手続き
| 1.相談 | サービス利用を希望する人は、市町村または相談支援事業者に相談します。相談支援事業者は、市町村の指定した事業所で、障害福祉サービスの申請前の相談や申請手続きの支援、サービスを利用する場合の計画書の作成、サービス事業者との連絡調整などを行います。 |
|---|---|
| 2.申請 | 相談を終えてサービス利用を希望することが決まったら、住んでいるところの市町村にサービス利用の申請を行います。現在施設に入所していて居住地がない場合は、入所前の居住地に申請を行います。児童の場合は申請手続きを保護者が行うこともできます。 |
| 3.審査・判定 | 申請を行うと市町村から現在の生活や障害に関して調査を受けます(アセスメント)。この調査結果をもとに市町村は審査・判定を行ない、どのくらいのサービスが必要かという障害支援区分を決定します。(認定審査会を行います。) |
| 4.認定・通知 | 障害支援区分や介護する人の状況、申請者の希望をもとにサービスの支給量が決まり通知されます。サービス利用者には「福祉サービス受給者証」が交付されます。 |
| 5.契約 | 支給決定が決まると相談支援事業者のサポートを受けて、サービス利用計画書を作成します。利用者が、計画作成にかかる費用を支払うことは原則ありません。計画が決定したらサービス提供事業者との契約を行います。 |
| 6.利用 | 契約が完了した段階でサービス利用が始まります。 |
※障害支援区分・・・障害者に対する介護給付の必要度を表す6段階の区分です。(区分が1~6、区分6の方が必要度は高い)