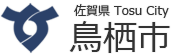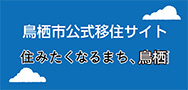本文
地震に備える
「鳥栖市では大きな地震もないし、活断層もないから安心だ」と考えている方が大半かもしれません。
しかし、久留米市を横断する形で水縄(みのう)断層という活断層の存在が確認されており、この活断層に原因して、西暦679年には幅6m、長さ10kmの地割れを生じる大地震が発生しています。
また、博多湾から筑紫野市にわたる全長27kmの警固(けご)断層は、平成17年3月に発生した福岡県西方沖地震の断層と一連の断層帯であると考えられています。今後30年の間に0.3%から6.0%の確率で地震が発生する可能性があり、断層全体が動いた場合には、マグニチュード7.2程度の規模の地震が予想されています。
鳥栖市でも、いつどのような地震が起きるかわかりません。地震に備え、日ごろより家庭での安全対策を十分に行うことが重要です。
地震の揺れと想定被害
|
震度 |
想定される被害 |
|---|---|
|
震度0 |
人は揺れを感じない。 |
|
震度1 |
屋内にいる人の一部がわずかな揺れを感じる。 |
|
震度2 |
屋内にいる人の多くが揺れを感じ、吊り下がりの電灯が揺れる。 |
|
震度3 |
屋内にいる人のほとんどが揺れを感じ、棚の食器が音を立てることがある。 |
|
震度4 |
眠っている人のほとんどが目を覚まし、部屋の不安定な物が倒れる。 歩行中の人も揺れを感じる。 |
|
震度5弱 |
家具が移動し、食器や本が棚から落ちる。 窓ガラスが割れることがある。 |
|
震度5強 |
タンスなど重い家具や、外では自動販売機が倒れることがある。 自動車の運転が困難になる。 |
|
震度6弱 |
立っていることが難しい。 壁のタイルや窓ガラスが壊れ、ドアが開かなくなる。 |
|
震度6強 |
立っていられず、はわないと動くことができない。 重い家具のほとんどが倒れ、戸がはずれて飛ぶ。 耐久性の低い建物は倒壊する。 |
|
震度7 |
自分の意志で行動できない。 大きな地割れや地すべり、山崩れが発生する。 ほとんどの建物が傾いたり、倒壊する。 |
家庭でできる日ごろの備えについて
- もしもの時の役割分担や連絡方法・集合場所を家族で話し合っておく。
- 家族の名前・住所・血液型・携帯番号などのメモやカードを作り持ち歩く。
- 目につくところに非常持出し品や消火器を準備しておく。
- 避難場所や避難所までの経路を確認しておく。
- 寝室、子供、お年寄りのいる部屋には、家具をなるべく置かないようにする。
- 家具、電化製品、ピアノなどは固定したり、すべり止めをつけるなどの対応をする。
- 家具などは人の出入りが少ない部屋にまとめて置くなど、逃げ場としての安全な空間をつくっておく。
- 安全に避難するため、出入り口や通路には物を置かないようにする。
地震が発生したら
- 災害時は、テレビやラジオなどから正確に情報収集をして、冷静に的確な行動をする。
- デマに惑わされないこと、パニックにならないことが大切
屋内で地震を感じたら
|
1 身の安全を守る |
|
|---|---|
| 2 火の始末をする |
|
| 3 脱出口の確保 |
|
| 4 災害情報を確認 |
|
| 5 危険な時は避難 |
|
屋外で地震を感じたら
|
1 身の安全を守る |
|
|---|---|
| 2 災害情報を確認 |
|
| 3 危険な時は避難 |
|
地震による避難時の注意点
- 避難する前に、もう一度火元を確かめる。(復旧後の二次災害を防ぐため、ガスの元栓を締め電気のブレーカーは切ります。)
- 家には避難先や安否情報を記したメモを残す。
- ラジオなどから正確に情報収集をし、冷静に的確な行動を心がける。
- ヘルメットなどで頭を保護し、長袖・長ズボンなどの安全な服を着用する。
- 必ず徒歩で避難する。(車を使用すると、渋滞を招いたり、救助活動に支障が出たりします。)
- 体の不自由な方、お年寄り、妊婦さんがいたら助け合う。
- 狭い道、川べり、がけのそば、塀や自動販売機のそば、ガラスや看板の多い場所を避けて避難する。
- できるだけ集団で避難する。
- 避難する時の荷物は、必要最小限の必需品にする。
- 携帯ラジオ、懐中電灯、ろうそく
- ヘルメット(防災ずきんなど)
- 非常食、水(火を通さないで食べられる物、赤ちゃんには粉ミルク、ベビーフード)
- 生活用品(ライター、缶切り、ティッシュ、ビニール袋、哺乳びんなど)
- 衣類(下着、上着、靴下、タオル、紙オムツなど)
- 救急薬品(ばんそうこう、ガーゼ、消毒薬、解熱剤、胃腸薬、かぜ薬など、持病のある人は常備薬も忘れずに)
- 通帳、証書等(預金通帳、保険証、免許証、印鑑等)
- 現金(紙幣だけでなく、公衆電話用の10円硬貨も用意)